こんにちは!テキエブの鳥山涼です。
こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!
ウイスキー品評会金賞 60年ぶり製造1本目 明利酒類 茨城・水戸
明利酒類(茨城県水戸市)が約60年ぶりに再開したウイスキー製造の第1弾「高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH」が、アジア最大級の蒸留酒品評会で金賞を受賞しました。加藤喬大常務は、酵母量を3倍に増やし発酵時間を1週間以上に延ばすことでフルーティーな味わいを実現し、同社の「百年梅酒」が染み込んだ樽の原酒を中心にブレンドしたことが高く評価されたと語っています。東京ウイスキー&スピリッツコンペティション洋酒部門には639アイテムが出品され、「高藏 NEW MAKE THE FIRST DROP」も銅賞を獲得しました。加藤常務は今後の原酒の成長に期待を寄せ、来夏には「高藏シングルモルト」の発売や茨城県産麦芽を使った「オール茨城」ウイスキーの製造計画を明かしています。受賞酒は茨城県内の酒販店やバーで楽しめます。 【参考URL】 茨城新聞記事:https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16859256000468
- 1 明利酒類が60年ぶりに再開したウイスキー製造の背景とは?
- 2 「高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH」の特徴と金賞受賞のポイント
- 3 加藤喬大常務が語る発酵技術の工夫と味わいの秘密
- 4 「百年梅酒」樽の原酒を使ったブレンドの魅力を解説
- 5 東京ウイスキー&スピリッツコンペティションの概要と評価基準
- 6 「高藏 NEW MAKE THE FIRST DROP」の銅賞受賞について
- 7 今後の展望:来夏発売予定の「高藏シングルモルト」と「オール茨城」ウイスキー計画
- 8 茨城県産麦芽の活用が示す地域産業との連携と可能性
- 9 受賞酒の入手方法と茨城県内の酒販店・バーでの楽しみ方
- 10 ウイスキー製造再開の意義と日本のウイスキー業界への影響
明利酒類が60年ぶりに再開したウイスキー製造の背景とは?

志乃さん、僕もすごく興味があります!60年ぶりの再開ってかなりの決断ですよね。明利酒類さんは元々梅酒で有名ですが、ウイスキーに戻る理由や背景について、もっと詳しく知りたいです。
地域の特産品を活かしたお酒作りも最近注目されているので、地元茨城での製造再開は面白い動きだと思います。
「高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH」の特徴と金賞受賞のポイント

今回金賞を受賞した「高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH」は、単なるウイスキーではなく、梅酒の樽でフィニッシュしたという点が大きな特徴よね。
梅酒の樽由来のフルーティーな香りと味わいが、ウイスキーに独特の深みを与えているのが評価されたポイントだと思うわ。

なるほど、梅酒の樽で熟成させることで、ウイスキーに新しい味わいが生まれるんですね!普通のウイスキーとは違う魅力があるということですね。
金賞を受賞したということは、味や品質が国際的にも認められた証拠ですよね。これはぜひ飲んでみたいです。
加藤喬大常務が語る発酵技術の工夫と味わいの秘密

加藤喬大常務が語る発酵の工夫も興味深いわ。酵母の量を3倍に増やし、発酵時間を1週間以上に延ばすことで、よりフルーティーな味わいを実現したそうよ。
これは発酵プロセスの細かな調整が、ウイスキーの風味に大きく影響することを示しているわね。

発酵時間を長くすることで、味わいがどう変わるのか具体的に教えてもらえますか?僕はまだ発酵の仕組みについて詳しくないので。
また、酵母の量を増やすことがどんな効果をもたらすのかも気になります。

良い質問ね。発酵時間を長くすると、酵母が糖分をより多く分解して、エステル類などの香り成分が増えるの。これがフルーティーな香りの元になるわ。
酵母の量を増やすことで発酵が活発になり、より豊かな香りと味わいが生まれるのよ。だからこの調整は、ウイスキーの個性を引き出す重要なポイントなの。
「百年梅酒」樽の原酒を使ったブレンドの魅力を解説

「高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH」は、同社の「百年梅酒」が染み込んだ樽の原酒を中心にブレンドされているのが特徴よ。
この「百年梅酒」は、長い歴史を持つ梅酒で、その樽の香りや味わいがウイスキーに移ることで、独特の深みと複雑さが生まれているの。

梅酒の樽を使うというのは珍しいですね。普通はシェリーやバーボンの樽が多いと思うのですが、梅酒樽だとどんな違いが出るんでしょう?
また、ブレンドの際に気をつけるポイントなどもあれば教えてください。

梅酒樽は、梅の果実由来の甘みや酸味、そして独特の香りが樽材に染み込んでいるため、ウイスキーにフルーティーで爽やかなニュアンスを加えるのよ。
ブレンドの際は、原酒同士のバランスを見極めて、梅酒樽由来の香りが強すぎず、ウイスキー本来の味わいを損なわないように調整することが重要ね。
東京ウイスキー&スピリッツコンペティションの概要と評価基準

東京ウイスキー&スピリッツコンペティションは、アジア最大級の蒸留酒品評会で、639アイテムが洋酒部門に出品されたの。
この規模の品評会で金賞を受賞するということは、非常に高い品質と独自性が認められた証拠よ。

639アイテムも出品されているんですね!競争が激しい中での金賞受賞はすごいことだと思います。
評価基準はどんなものがあるんですか?味だけでなく香りや見た目も関係するんでしょうか?

そうね、評価は香り、味わい、バランス、後味、そして全体の完成度など多角的に行われるわ。
また、独創性や地域性も評価のポイントになることが多いの。だから「高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH」のようなユニークな製法は高く評価されやすいのよ。
「高藏 NEW MAKE THE FIRST DROP」の銅賞受賞について

同じく明利酒類の「高藏 NEW MAKE THE FIRST DROP」も銅賞を獲得しているわね。これは蒸留直後の原酒で、ウイスキーの素の味を楽しめる貴重なアイテムよ。
銅賞受賞は、まだ熟成前の段階でも高いポテンシャルを持っていることを示しているわ。

熟成前の原酒が評価されるのは珍しい気がします。どんな味わいが特徴なんでしょうか?
また、この原酒が今後どのように成長していくのか、楽しみですね。

原酒はまだ荒々しさもあるけれど、フルーティーで爽やかな香りが感じられるわ。これが熟成を経てまろやかに変化していくのがウイスキーの醍醐味ね。
加藤常務も今後の原酒の成長に期待を寄せているので、来夏発売予定の「高藏シングルモルト」への期待が高まるわね。
今後の展望:来夏発売予定の「高藏シングルモルト」と「オール茨城」ウイスキー計画

加藤常務は来夏に「高藏シングルモルト」の発売を予定していると明かしているわ。また、茨城県産の麦芽を使った「オール茨城」ウイスキーの製造計画も進んでいるの。
これは地域の素材を活かしたウイスキー作りの新たな挑戦で、地域産業との連携も期待されているわね。

地元産の麦芽を使うことで、どんな特徴が出るんでしょうか?地域の気候や土壌も味に影響するんですか?
それにしても、地域密着型のウイスキー作りは、消費者にとっても魅力的ですね。

そうね、麦芽の品種や栽培環境は発酵や味わいに大きく影響するわ。茨城県産の麦芽を使うことで、地域独自の個性を持ったウイスキーが生まれる可能性が高いの。
地域の気候や水質も加わって、唯一無二の味わいになるわよ。こうした取り組みは日本のウイスキー業界の多様化にも貢献するわね。
茨城県産麦芽の活用が示す地域産業との連携と可能性

茨城県産麦芽の活用は、単に原料調達の面だけでなく、地域産業全体の活性化にもつながるわ。
農業、製造業、観光業など多方面に波及効果が期待できるの。これはウイスキー作りが地域経済に与える良い影響の一例ね。

なるほど、ウイスキーの製造が地域の雇用や観光にも貢献するんですね。僕も地元の特産品を使ったお酒が増えるのは嬉しいです。
こうした取り組みが他の地域にも広がると、日本のウイスキー文化がさらに豊かになりそうですね。

その通りよ。地域の特色を活かしたウイスキー作りは、消費者にも新しい発見をもたらすし、業界全体の活性化にもつながるわ。
明利酒類の挑戦は、今後の日本のウイスキー業界にとっても重要なモデルケースになると思うわ。
受賞酒の入手方法と茨城県内の酒販店・バーでの楽しみ方

今回の受賞酒は茨城県内の酒販店やバーで楽しめるそうよ。地元でしか味わえない貴重なウイスキーを体験できるのは嬉しいわね。
詳しくは茨城新聞の記事(こちら)で紹介されているから、興味がある人はチェックしてみて。

地元の酒販店やバーで飲めるのはいいですね!僕も茨城に行く機会があれば、ぜひ味わってみたいです。
また、バーでのおすすめの飲み方やペアリングなどもあれば教えてください。

「高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH」は、ストレートやロックでそのフルーティーな香りを楽しむのがおすすめよ。
また、軽く炭酸で割ってカクテルベースにしても、梅酒樽由来の爽やかさが活きて美味しいわ。食事とのペアリングなら、和食や軽めのチーズが合うと思うわよ。
ウイスキー製造再開の意義と日本のウイスキー業界への影響

明利酒類のウイスキー製造再開は、日本のウイスキー業界にとっても大きな意味を持つわ。新たなプレイヤーが加わることで、業界全体の競争力や多様性が高まるから。
特に地域資源を活かした個性的なウイスキーの登場は、国内外の市場での差別化につながるわね。

そうですね。日本のウイスキーは世界的にも評価が高まっていますが、こうした新しい挑戦がさらに業界を盛り上げるんですね。
僕もこれからもっとウイスキーについて学んで、いろんな銘柄を試してみたいと思います。志乃さん、今日もありがとうございました!

こちらこそ涼くん。これからも新しい情報を一緒に追いかけていきましょうね。
ウイスキーの世界は奥が深いけれど、その分楽しみも大きいから、ぜひ色々試してみて。



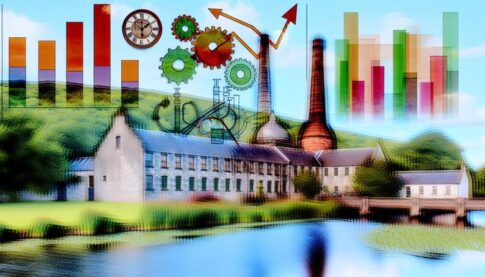

















明利酒類が約60年ぶりにウイスキー製造を再開したというニュースは、業界にとって非常に注目すべき出来事ね。長い間ウイスキー製造から離れていた企業が再び挑戦する背景には、どんな狙いがあるのかしら?
特に、茨城県水戸市という地域での再開は、地元の酒造業界や地域活性化にもつながる可能性が高いわ。涼くんはどう思う?