こんにちは!テキエブの鳥山涼です。
こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!
日光杉並木和だる熟成ウイスキー 日光東照宮に2種献上 10月限定販売へ 小山の西堀酒造
栃木県小山市の清酒蔵元「西堀酒造」が、日光杉並木街道の杉材で作った和だる(和樽)を使って熟成させたウイスキー「日光東照宮御神木・杉和樽ウヰスキー」を製造。10月に限定販売される2種類のウイスキーが、日光東照宮で行われた献上祭で奉納された。今年は杉並木街道の植樹400年の節目にあたり、同東照宮の協力のもと企画された。県内初のウイスキー蒸留所として注目される西堀酒造の新たな挑戦となっている。詳細は西堀酒造の公式情報をご確認ください。
西堀酒造が挑む栃木県初のウイスキー蒸留とその背景

志乃さん、酒蔵がウイスキーを作るって珍しいですよね。日本酒とウイスキーって全然違うお酒だと思うんですが、どうして挑戦したんでしょう?

確かに製造方法や原料は異なるけれど、発酵や蒸留の技術は共通点も多いの。西堀酒造は、地元の素材や文化を活かしながら新しい価値を生み出そうとしているのよ。
栃木県初のウイスキー蒸留所としての挑戦は、地域の酒文化の幅を広げる重要な一歩と言えるわね。

なるほど、地域の伝統を守りつつ新しいことに挑戦するって、すごく意義があるんですね。これからの展開が楽しみです!
日光杉並木の杉材を使った「和だる」熟成の特徴とは?

今回のウイスキーの最大の特徴は、日光杉並木街道の杉材で作られた「和だる」、つまり和樽を使って熟成させていることよ。
杉の木は日本の伝統的な建築や工芸に使われてきた素材で、独特の香りや風味をウイスキーに与えることができるの。

杉の樽でウイスキーを熟成させるって珍しいですよね。普通はオーク樽が使われるって聞きますけど、杉だとどんな違いがあるんですか?

そうね、オーク樽はバニラやキャラメルのような甘い香りをウイスキーに与えるけど、杉樽はもっと爽やかで清涼感のある香りが特徴的よ。
また、杉は日本の気候風土に合った素材だから、和のテイストを強調しつつ、ウイスキーに新しい個性をもたらすことができるの。この和樽熟成は、伝統と革新の融合の象徴と言えるわね。

なるほど、杉の香りがウイスキーにどう影響するのか、ぜひ味わってみたいです。和の素材を使うことで、どんな味わいになるのか気になります!
「日光東照宮御神木・杉和樽ウヰスキー」2種の限定販売について

西堀酒造は、この杉和樽ウイスキーを2種類、10月に限定販売する予定よ。
名前も「日光東照宮御神木・杉和樽ウヰスキー」として、日光東照宮の御神木の杉材を使っていることを強調しているわ。

限定販売なんですね!やっぱり御神木の杉を使っているっていうのが特別感を出しているんでしょうか?

そうよ。日光東照宮は歴史的にも非常に重要な場所で、その御神木を使うことで、単なるウイスキー以上の価値を持たせているの。
また、2種類のウイスキーはそれぞれ熟成期間や樽の使い方が異なり、味わいの違いを楽しめるようになっているわ。詳細は西堀酒造の公式情報で確認できるから、興味がある人はぜひチェックしてみて。

ありがとうございます!限定品って聞くと、つい手に入れたくなりますね。志乃さんも飲んでみたいですか?

もちろんよ。和樽熟成のウイスキーは珍しいし、味わいの幅も広そうだから、じっくりテイスティングしてみたいわね。
日光東照宮への献上祭と植樹400年の節目が意味するもの

このウイスキーは、日光東照宮で行われた献上祭で奉納されたのも大きな話題よ。
今年は杉並木街道の植樹400年の節目の年であり、東照宮の協力のもと企画されたことが、地域の歴史や文化との深い結びつきを示しているわ。

400年も続く杉並木の歴史とウイスキーが結びつくなんて、すごくロマンがありますね。献上祭ってどんな意味があるんですか?

献上祭は、神様に感謝や祈りを捧げる儀式で、特別な品を奉納することで地域の繁栄や安全を願う伝統行事よ。
今回のウイスキーの奉納は、単なる商品販売以上に、地域の誇りや歴史を未来へつなぐ象徴的な意味を持っているの。地域文化と酒造りの融合が感じられる貴重な機会ね。

なるほど、歴史的な節目に合わせて作られたお酒だからこそ、特別な価値があるんですね。そういう背景を知ると、飲むときの気持ちも変わりそうです。
和樽熟成ウイスキーの味わいと日本酒蔵元ならではの技術解説

西堀酒造は日本酒蔵元としての長年の経験を活かし、発酵や蒸留の技術をウイスキー製造に応用しているのがポイントよ。
特に和樽熟成は、杉の香りだけでなく、日本酒造りで培った微妙な温度管理や熟成環境のノウハウが活きているわ。

日本酒の技術がウイスキーにどう影響するのか、具体的にはどんなところが違うんでしょう?

例えば、発酵段階での酵母の選定や管理、蒸留時の温度調整、そして熟成中の環境管理は、日本酒造りで培った繊細な技術が役立っているの。
これにより、杉和樽の個性を最大限に引き出しつつ、バランスの良い味わいを実現しているのよ。日本酒蔵元ならではの技術融合が、独自のウイスキーを生み出していると言えるわね。

技術の融合が味にどう反映されているのか、ますます興味が湧きました。和樽熟成のウイスキー、ぜひ味わってみたいです!
西堀酒造の今後の展望と地域活性化への期待

西堀酒造のこの挑戦は、単に新商品を出すだけでなく、地域の活性化にもつながる期待が大きいわ。
地元の素材や歴史を活かした酒造りは、観光や地域ブランドの強化にも寄与するから、今後の展開が注目されているの。

地域の歴史や素材を活かしたお酒作りって、地元の人にも観光客にも喜ばれそうですね。西堀酒造はこれからどんな展望を持っているんでしょう?

今後は、今回の杉和樽ウイスキーを軸に、さらなる商品開発や地域連携を進めていく計画があるみたいよ。
また、ウイスキーの品質向上とともに、地元の歴史や文化を発信する役割も担うことで、地域全体の魅力アップに貢献できるはず。西堀酒造の挑戦は、地域と共に成長するモデルケースとして期待されているわね。

志乃さん、今日はたくさん勉強になりました。西堀酒造のウイスキー、ぜひ注目していきたいです。ありがとうございました!

こちらこそ涼くん、興味を持ってくれて嬉しいわ。これからも一緒にお酒の世界を楽しみましょうね。





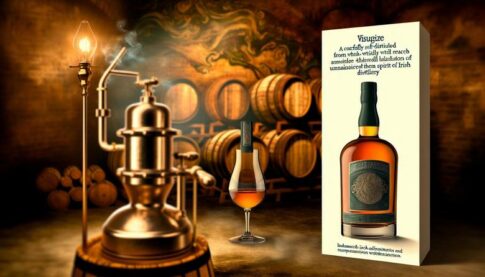










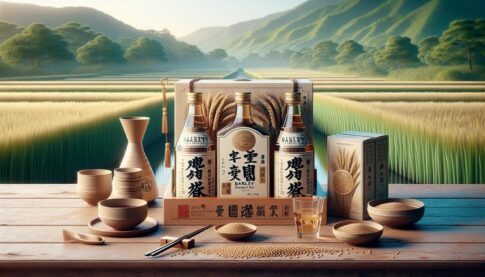




栃木県小山市にある西堀酒造が、県内初のウイスキー蒸留に挑戦しているのをご存知?
これまで日本酒蔵元として知られていた西堀酒造が、新たにウイスキー製造に乗り出したのは、地域の伝統と革新を融合させる試みとして注目されているわ。