こんにちは!テキエブの鳥山涼です。
こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!
岩手・盛岡のクラフトビールメーカー・ベアレン醸造所、農業から消費者までつなぐ 地域循環型経済の試み – 日本経済新聞
岩手・盛岡のクラフトビールメーカー、ベアレン醸造所が2025年4月に発売した「つなぐビール」が好調なスタートを切りました。このビールは原料の大麦麦芽とホップを100%岩手県産にこだわっており、農業生産者から消費者までをビールを通じて結びつける地域循環型経済の全国初の試みとして注目されています。具体的には、紫波町の高橋農園で栽培される大麦「小春二条」など地元産原料を活用し、地域の農業振興と地産地消を推進しています。詳細は日本経済新聞の会員限定記事で紹介されています。 記事URL(日本経済新聞・ベアレン醸造所の地域循環型経済の試み) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD2170B0R20C24A7000000/
岩手・盛岡のベアレン醸造所とは?その歴史と特徴を解説

志乃さん、そうなんですね!僕はまだクラフトビールのことをあまり詳しく知らなくて、地元の素材にこだわっているっていうのはすごく興味深いです。ベアレン醸造所は盛岡のどんなところで愛されているんですか?
あと、ドイツの伝統製法ってどんな感じなんでしょう?教えてください。

いい質問ね。ベアレンは盛岡の地元の人たちだけでなく、観光客にも人気があって、地元の食材と合わせて楽しむスタイルが定着しているわ。ドイツ伝統製法は、例えばラガービールの低温発酵を用いることで、クリアでキレの良い味わいを生み出すのが特徴よ。
それに加えて、ベアレンは小規模生産ならではの手間暇かけた製造をしているから、味に深みがあるの。こうしたこだわりがクラフトビールファンの心を掴んでいるのよ。
「つなぐビール」誕生の背景と地域循環型経済の狙い

ベアレン醸造所が2025年4月に発売した「つなぐビール」って、名前からして何か意味がありそうですね。どんなビールなんですか?
それに、地域循環型経済って聞き慣れない言葉ですが、どういう狙いがあるんでしょうか?

「つなぐビール」は、岩手県産の大麦麦芽とホップを100%使ったビールで、農業生産者と消費者をビールを通じて結びつけることを目的にしているの。つまり、地域の農産物を活用して、地元経済を循環させる全国初の試みなのよ。
地元の農家が育てた原料を使うことで、農業振興と地産地消を同時に推進しているのが大きな特徴ね。涼くん、こうした地域密着型の取り組みはクラフトビール業界でも珍しいと思わない?

確かに、ビールを作るだけじゃなくて、地域の農業や経済にまで影響を与えるってすごいですね。単なる商品開発を超えた社会的な意義があるんだなと感じました。
志乃さん、こういう取り組みは他の地域や業界にも広がっていくんでしょうか?

可能性は大いにあるわね。地域の特産品を活かすことで、消費者も生産者も双方にメリットがあるから、持続可能な経済モデルとして注目されているのよ。
ただし、原料の安定供給や品質管理など課題もあるから、成功には地元の強い連携と長期的な視点が必要になるわね。
岩手県産100%の原料「小春二条」とホップの魅力

「つなぐビール」の原料には、紫波町の高橋農園で栽培される大麦「小春二条」が使われているの。これは岩手県で育てられた二条大麦の品種で、ビール用麦芽としての品質が高いことで知られているわ。
また、ホップも岩手県産にこだわっているから、香りや苦味のバランスが地域の気候風土を反映した独特の味わいを生み出しているのよ。

大麦の品種までこだわっているんですね。小春二条って、どんな特徴があるんですか?
ホップも地元産だと、どんな違いが出るんでしょうか?

小春二条は、耐寒性が強く、岩手の気候に適しているから安定した収穫が見込めるの。麦芽にすると、麦の甘みとコクがしっかり出るのが特徴ね。
ホップは香り成分が豊かで、苦味が爽やか。地元産だからこそ、フレッシュで個性的な香りがビールに活きているの。こうした原料の選定が地域の味を表現する重要なポイントになっているのよ。
農業生産者と消費者をつなぐ新しいビールの役割とは?

「つなぐビール」は名前の通り、生産者と消費者をつなぐ役割があるんですね。具体的にはどんな仕組みでつながっているんでしょう?

このビールは、農家が育てた原料を使うことで、生産者の収益向上に直接つながる仕組みになっているの。さらに、消費者は地元の素材を味わうことで、地域の農業や経済に貢献している実感を持てるわ。
つまり、ビールを飲むことが地域の活性化に参加することになるの。こうした双方向のつながりが新しい消費の形として注目されているのよ。

なるほど、ただの飲み物じゃなくて、地域の人たちの暮らしや産業を支える存在になっているんですね。僕もそういうビールを飲んでみたいです。
志乃さん、こういう取り組みは消費者の意識にも変化をもたらしそうですね?

その通り。消費者が生産背景を知ることで、より愛着が湧き、リピートや口コミにもつながるわ。クラフトビールのファン層拡大にも貢献すると思うわよ。
地域循環型経済の全国初の試みがもたらす業界への影響

ベアレン醸造所の地域循環型経済への挑戦は、クラフトビール業界だけでなく、広く食品・飲料業界にも影響を与える可能性があるわ。
地元産原料の活用と地域経済の活性化を両立させるモデルは、持続可能なビジネスの新しい形として注目されているのよ。

そうすると、他の地域でも同じような取り組みが増えていくかもしれませんね。業界全体のトレンドにもなりそうです。
志乃さん、実際にこうした動きが広がるためにはどんな課題があるんでしょう?

課題は多いわね。例えば、原料の安定供給や品質の均一化、コスト面の問題もあるわ。さらに、地域間の連携や行政の支援も重要になるわね。
でも、成功すれば地域の魅力発信や観光促進にもつながるから、長期的に見れば大きなメリットが期待できるわ。
ベアレン醸造所の今後の展望とクラフトビール市場の動向

ベアレン醸造所は今後どんな展望を持っているんでしょうか?クラフトビール市場の動向も気になります。
志乃さん、教えてください。

ベアレンは地域密着型の製品開発を続けつつ、全国や海外への展開も視野に入れているわ。クラフトビール市場は多様化が進み、消費者の嗜好も細分化しているから、独自性が重要になるのよ。
「つなぐビール」のような地域循環型の取り組みは、差別化の強みになるし、消費者の支持も得やすいわね。市場全体としては、品質とストーリー性を兼ね備えた商品が求められているわ。

なるほど、品質だけじゃなくて、背景や物語も大事なんですね。僕もそういうビールをSNSで紹介してみたいです。
志乃さん、僕みたいな若い世代がクラフトビールにもっと興味を持つにはどうしたらいいでしょう?

まずは色々なスタイルのクラフトビールを試してみることね。味の違いや原料の特徴を知ると、もっと楽しめるわ。
そして、背景にある地域や生産者のストーリーを知ることで、飲む体験が豊かになるわよ。SNSで発信するのも素敵な方法ね。
お酒好き必見!クラフトビールの基本知識と楽しみ方

クラフトビールは大手メーカーのビールと違い、小規模で個性的な味わいが特徴よ。原料や製法にこだわり、地域性が色濃く反映されるのが魅力ね。
楽しみ方としては、まず香りをしっかり感じてから味わうこと。温度やグラスの形状も味に影響するから、試してみるといいわ。

香りを楽しむんですね。僕はいつもゴクゴク飲んじゃうので、これからはゆっくり味わってみます。
志乃さん、クラフトビールに合うおつまみとかありますか?

ビールのスタイルによって合うおつまみは変わるけど、例えば「つなぐビール」のような麦芽の甘みとホップの爽やかな苦味があるビールなら、地元のチーズや燻製、ナッツ類がよく合うわ。
また、地域の食材と合わせることで、より一層味わいが引き立つの。ぜひ色々試してみてね。
余談:岩手の地酒文化とクラフトビールの共存可能性について

岩手県は日本酒も有名ですよね。地酒文化とクラフトビールはどう共存していけるんでしょう?
志乃さん、教えてください。

岩手は酒どころとしても知られていて、日本酒の伝統が根強いわね。でもクラフトビールも地域の新しい魅力として注目されているのよ。
両者は競合ではなく、むしろ共存・共栄できる関係だと思うわ。例えば、地元の飲食店で日本酒とクラフトビールのペアリングを提案したり、地域のイベントで両方を楽しめる機会を作ることが考えられるわね。

なるほど、地元の魅力を多角的に発信することで、観光や地域活性化にもつながるんですね。
志乃さん、僕もそういうイベントに参加してみたいです!

ぜひ参加してみて。実際に体験すると、地域の文化やお酒の奥深さがもっとわかるわよ。
ちなみに詳しい内容は日本経済新聞の会員限定記事で紹介されているから、興味があればこちらの記事もチェックしてみてね。






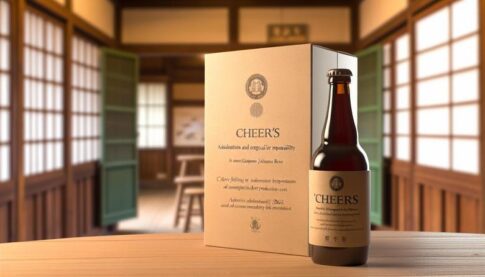





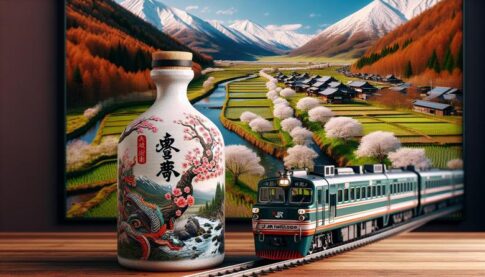
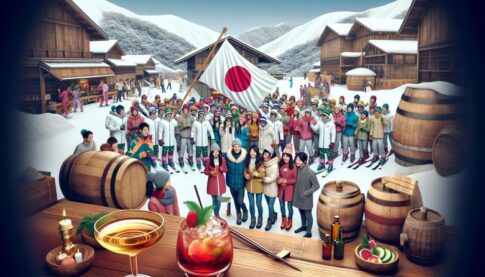







岩手県盛岡市に拠点を置くベアレン醸造所は、1997年に創業したクラフトビールメーカーで、ドイツ伝統の製法をベースにしたビール造りが特徴よ。地元の素材を活かしつつ、丁寧な手作り感を大切にしているのが魅力ね。
特に東北地方の気候や風土に合った味わいを追求していて、地域に根ざしたクラフトビール文化の発展に貢献しているわ。涼くん、クラフトビールって最近ますます注目されているけど、ベアレンのような地元密着型の醸造所が増えているのは知ってる?