こんにちは!テキエブの鳥山涼です。
こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!
Yahoo!ニュース
サントリーの大阪工場が2026年春から一般見学ツアーを開始することが発表されました。代表的なジン銘柄であるジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」は、2017年の発売以来8年で世界第2位のプレミアムジンに成長(2024年販売数量/IWSR2025データ)。ジンのルーツはオランダの薬用酒で、ジュニパーベリー(西洋ねずの実)が不可欠なボタニカルです。近年のジントレンドは欧州発のクラフトジンムーブメントに起因し、サントリーも2017年に「ROKU〈六〉」、2020年に「翠(SUI)」を発売。特に「翠(SUI)」はソーダ割りのフードペアリング提案や2022年の「翠ジンソーダ缶」のヒットで市場を牽引しています。国内の小規模蒸溜所は約140にのぼり、缶入りジンソーダやジントニックも定着しています。工場見学ではジュニパーベリーをはじめとしたボタニカルの実物や香りを体験可能です。 【関連記事】 ・サントリー「翠ジンソーダ缶〈瀬戸内レモン搾り〉」期間限定発売 ・サントリー京都ビール工場見学ツアーの独自性 ・原酒のソーダ割りブームとおすすめ銘柄18 ・サントリー「翠ジンソーダ缶〈柚子搾り〉」再発売 詳細記事(GetNavi web/Yahoo!ニュース): https://news.yahoo.co.jp/articles/xxxxxxxxxxxxxx (※元記事URLは入力文に記載なしのため、実際のURLはご確認ください)
- 1 サントリー大阪工場の一般見学ツアー開始発表
- 2 ジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の世界的成功とその背景
- 3 ジンのルーツとジュニパーベリーの重要性について
- 4 近年のジントレンドと欧州クラフトジンムーブメントの影響
- 5 サントリーのジンブランド「ROKU〈六〉」と「翠(SUI)」の特徴と市場展開
- 6 「翠ジンソーダ缶」のヒットとフードペアリング提案の効果
- 7 国内小規模蒸溜所の現状と缶入りジンソーダ・ジントニックの定着
- 8 工場見学で体験できるボタニカルの香りと実物の魅力
- 9 関連記事紹介:期間限定「翠ジンソーダ缶〈瀬戸内レモン搾り〉」と再発売「柚子搾り」
- 10 まとめ:ジン市場の最新動向と今後の展望について葉山志乃と鳥山涼の対話
サントリー大阪工場の一般見学ツアー開始発表

そうなんですね、志乃さん。僕も工場見学はまだ行ったことがないので、すごく興味があります。特にジンのボタニカルの香りを実際に体験できるのは面白そうです。
大阪工場はどんな特徴があるんでしょうか?ジンの製造に特化しているんですか?

大阪工場はサントリーの主要な蒸溜所の一つで、特にクラフトジンの製造に力を入れているわ。ここで作られる「ROKU〈六〉」は世界的にも評価が高いから、製造現場を見られるのは貴重な体験になるはずよ。
製造工程の見学とボタニカルの香り体験がセットになっているのは、ジンファンにとって魅力的なポイントね。
ジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の世界的成功とその背景

「ROKU〈六〉」は2017年に発売されてからわずか8年で、世界第2位のプレミアムジンに成長したそうですね。すごい人気なんですね!
どうしてそんなに評価が高いんでしょうか?

ROKU〈六〉の成功は、日本の四季折々のボタニカルを6種類使った独自のレシピにあるわ。桜の花や煎茶、山椒など、日本ならではの素材が織りなす繊細な香りと味わいが世界中のジン愛好家に評価されているの。
さらに、サントリーの品質管理と製造技術の高さも大きな要因ね。世界市場での販売数量はIWSRの2025年データで世界第2位に位置付けられているのよ。

なるほど、日本の素材を活かしたジンだからこそ、海外でも注目されているんですね。僕も一度飲んでみたいです。
ちなみに、ROKU〈六〉の特徴的なボタニカルはどんなものがあるんですか?

ROKU〈六〉には、ジュニパーベリーはもちろん、桜の花、桜の葉、煎茶、山椒、柚子の6種類のボタニカルが使われているわ。これらが絶妙に調和して、和の繊細さとクラフトジンの爽やかさを両立しているの。
この独自性が世界的な評価につながっているのよ。
ジンのルーツとジュニパーベリーの重要性について

ジンのルーツはオランダの薬用酒だと聞きましたが、ジュニパーベリーが不可欠なボタニカルだというのはどういうことですか?
ジュニパーベリーってどんな役割があるんでしょう?

ジュニパーベリーはジンの香りの核になるボタニカルで、ジンの定義上、必ず使われるものなの。薬用酒として始まったジンは、ジュニパーベリーの爽やかな松のような香りが特徴で、これがジンのアイデンティティを形作っているわ。
だから、どんなクラフトジンでもジュニパーベリーは欠かせないのよ。

なるほど、ジュニパーベリーがなければジンとは呼べないんですね。ジンの香りの基本なんですね。
他のボタニカルは香りや味わいのアクセントとして使われるんですか?

そうよ。ジュニパーベリーがベースの香りを作り、その上に柑橘類やスパイス、ハーブなどのボタニカルが重なって複雑で個性的な味わいになるの。
ROKU〈六〉のように日本の素材を使うことで、独特の和の風味が生まれるのも面白いポイントね。
近年のジントレンドと欧州クラフトジンムーブメントの影響

最近のジントレンドは欧州のクラフトジンムーブメントが影響していると聞きましたが、具体的にはどんな動きなんでしょう?

欧州では地元のボタニカルを使った小規模蒸溜所が増え、個性的なクラフトジンが続々と登場しているの。これが世界的なジン人気の高まりを後押ししているわ。
日本でもその影響を受けて、サントリーが2017年にROKU〈六〉、2020年に翠(SUI)を発売したのはその流れの一環ね。

なるほど、地元の素材や独自の製法で個性を出すのがクラフトジンの特徴なんですね。
日本のジン市場もその影響で活性化しているんですね。

そう。欧州のクラフトジンムーブメントが日本のジン市場の多様化と品質向上に大きく貢献しているのよ。これが今のジントレンドの背景にあるわ。
サントリーのジンブランド「ROKU〈六〉」と「翠(SUI)」の特徴と市場展開

サントリーのジンブランドにはROKU〈六〉のほかに「翠(SUI)」もありますが、両者の違いや特徴は何でしょうか?

ROKU〈六〉はクラフトジンとしての繊細な和のボタニカルが特徴で、プレミアム市場を狙った高級感のあるジンね。
一方で翠(SUI)は、よりカジュアルに楽しめるジンで、特にソーダ割りに適した味わいが特徴よ。2022年には「翠ジンソーダ缶」も発売されて、市場を牽引しているわ。

なるほど、ROKU〈六〉はじっくり味わうプレミアムジン、翠(SUI)は手軽に楽しめるジンという感じですね。
翠(SUI)のソーダ割りってどんな魅力があるんでしょう?

翠(SUI)は柑橘系の爽やかな香りと軽やかな味わいが特徴で、ソーダ割りにするとすっきりと飲みやすくなるの。これがフードペアリングにも合いやすく、食事と一緒に楽しむスタイルを提案しているのよ。
市場展開としても缶入りジンソーダのヒットが、ジンの新しい飲み方を広げているのがポイントね。
「翠ジンソーダ缶」のヒットとフードペアリング提案の効果

「翠ジンソーダ缶」は2022年にヒットしたそうですが、どんな点が人気の理由なんでしょう?

まず、缶入りで手軽に楽しめる点が大きいわね。さらに、瀬戸内レモン搾りや柚子搾りなど、和の柑橘を使った期間限定フレーバーも人気を後押ししているの。
これらのフレーバーは日本の食文化に合いやすく、フードペアリングの提案が市場での支持を集めているのよ。

なるほど、和の柑橘が入ることでより日本人の味覚に合うんですね。食事と一緒に楽しむのにぴったりだと思います。
期間限定のフレーバーも気になります。どんな種類があるんですか?

例えば「翠ジンソーダ缶〈瀬戸内レモン搾り〉」や「翠ジンソーダ缶〈柚子搾り〉」があって、どちらも期間限定で発売されているわ。これらはサントリーの公式サイトやニュース記事で詳細が紹介されているから、興味があればチェックしてみてね。
(参考記事:GetNavi web/Yahoo!ニュース)
国内小規模蒸溜所の現状と缶入りジンソーダ・ジントニックの定着

国内の小規模蒸溜所は約140もあるそうですが、これはどんな意味を持つんでしょう?
缶入りジンソーダやジントニックも定着していると聞きましたが、これらの関係は?

小規模蒸溜所の増加は、ジン市場の多様化と地域性の強化を意味しているわ。地元の素材を使った個性的なジンが増え、消費者の選択肢が広がっているの。
缶入りジンソーダやジントニックの定着は、こうした多様なジンを手軽に楽しむスタイルが浸透している証拠ね。忙しい現代人にとって、缶入りは便利でありながら質の高い味わいを提供しているのよ。

なるほど、蒸溜所の増加と缶入り商品の普及が相乗効果を生んでいるんですね。
これからも新しいジンの楽しみ方が広がりそうで楽しみです。
工場見学で体験できるボタニカルの香りと実物の魅力

工場見学ではジュニパーベリーをはじめとしたボタニカルの実物や香りを体験できるそうですが、これはどんな体験になるんでしょう?

実際にボタニカルの香りを嗅ぐことで、ジンの味わいのイメージが具体的になるわ。香りは味覚と密接に結びついているから、五感でジンを理解する貴重な機会になるのよ。
特にジュニパーベリーの香りはジンの基本だから、これを体験できるのはファンにとって嬉しいポイントね。

そうなんですね。実物を見て香りを嗅ぐことで、ジンの奥深さをより感じられそうです。
工場見学はジンの知識を深めたい人にとって、すごく価値のある体験になりそうですね。
関連記事紹介:期間限定「翠ジンソーダ缶〈瀬戸内レモン搾り〉」と再発売「柚子搾り」

サントリーは「翠ジンソーダ缶〈瀬戸内レモン搾り〉」を期間限定で発売しているほか、「柚子搾り」も再発売しているわ。これらは和の柑橘を活かしたフレーバーで、ジンソーダの新しい楽しみ方を提案しているの。
こうした限定商品は市場の注目を集めるだけでなく、消費者の興味を引き続ける役割も果たしているのよ。

期間限定や再発売のフレーバーは、ジンファンにとっては見逃せないですね。どこで情報をチェックすればいいですか?

公式のニュース記事やサントリーのウェブサイト、そして今回のようなニュース記事をこまめにチェックするといいわ。今回のニュースの詳細はこちらからも確認できるから参考にしてね。
こうした情報収集が、より深くお酒を楽しむコツよ。
まとめ:ジン市場の最新動向と今後の展望について葉山志乃と鳥山涼の対話

今回のニュースを通じて、ジン市場が多様化し、クラフトジンの人気が高まっていることがよく分かりました。特にROKU〈六〉の世界的成功は驚きです。
工場見学もぜひ行ってみたいと思います。志乃さん、今後のジン市場の展望についてどう思われますか?

ジン市場は今後もクラフトジンの多様化と、手軽に楽しめる缶入りジンソーダの普及が進むと予想しているわ。
日本独自のボタニカルを活かしたジンがさらに注目され、海外市場でも存在感を増していくはずよ。
また、工場見学のような体験型のイベントが増えることで、消費者の理解と愛着も深まると思うわ。涼くんもこれから色々なジンを試して、自分の好みを見つけてみてね。

ありがとうございます、志乃さん。僕ももっとジンの知識を深めて、いろんな楽しみ方を発信していきたいです。
今回のサントリー大阪工場の見学ツアー開始は、ジンファンにとって大きなニュースですね。今後の動きにも注目していきます。




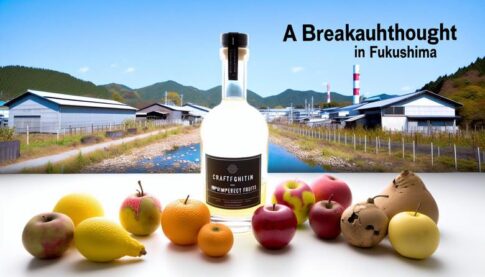
















サントリーの大阪工場が2026年春から一般見学ツアーを開始することが発表されたわ。これはお酒好きや業界関係者にとって貴重な機会になると思うの。工場見学では製造工程だけでなく、ジンのボタニカルの香りや実物も体験できるそうよ。
涼くん、工場見学ってお酒の理解を深めるうえでとても大切な体験だと思わない?実際に香りを嗅いだり、製造の裏側を知ることで、味わいの感じ方も変わってくるからね。