こんにちは!テキエブの鳥山涼です。
こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!
東急グループのソムリエが一丸となって実現 グループの力を結集し、オリジナルワインを販売 | ホテル・レストラン・ウエディング業界ニュース | 月刊ホテレス HOTERESONLINE
東急グループのソムリエが連携し、長野県産のオリジナルワイン「信州 片丘メルロ 紫紺 2023」を開発・販売しました。これは2025年2月に東急と長野県が締結した包括連携協定の一環で、長野県産品の販路拡大と消費促進を目的としています。東急百貨店、ながの東急百貨店、東急ストア、東急ホテルズ&リゾーツの4社が協力し、長野県塩尻市のワイナリー「ドメーヌ コーセイ」から一樽を購入。約30名のソムリエが参加した2024年2月の「ソムリエカンファレンス」での意見をもとに、6人の代表者が現地でテイスティングを行い、2023年産メルロをアメリカンオークで熟成させたワインを選定しました。各社の異なる顧客層や利用シーンに対応するため、最終的にこのワインに決定。2025年6月から東急グループの百貨店、スーパー、ホテルで276本限定で販売・提供を開始し、なくなり次第終了となります。 また、第2弾のオリジナルワインは長野県高山村の「信州たかやまワイナリー」と連携し、2025年秋に販売予定。さらに、2025年5月に締結した東急と北海道の包括連携協定に基づき、今後は北海道産品の消費拡大にも取り組む計画です。 詳細は月刊ホテレス2025年9月号およびHOTERES ONLINEで確認できます。 URL:https://www.hoteresonline.com/news/industry/20250912_tokyu_wine.html(※記事URLはニュース元参照)
東急グループと長野県の包括連携協定とは?

志乃さん、確かに地域の特産品が大手の流通網を通じて広まるのはすごく重要ですね。特にワインのように産地の個性が味に反映されるお酒は、地域の魅力を伝えるツールにもなりますし、消費者にとっても新しい発見があると思います。
それに、こうした連携があると、地元の小規模生産者も支援されやすくなるんじゃないでしょうか?

その通り。地域の生産者が安定した販路を確保できることは、品質向上や新商品の開発にもつながるわ。お酒の世界では特に、産地のストーリーや背景が商品の価値を高めるから、こうした包括連携は今後ますます重要になるでしょうね。
オリジナルワイン「信州 片丘メルロ 紫紺 2023」の誕生秘話

今回のニュースの主役、「信州 片丘メルロ 紫紺 2023」ってどんなワインなんですか?名前からして特別感がありますよね。

はい、このワインは長野県塩尻市のワイナリー「ドメーヌ コーセイ」が手掛けた2023年産のメルロを使っているの。メルロはフルーティーで柔らかいタンニンが特徴の赤ワイン用ブドウ品種で、世界中で人気が高いわ。
このワインは特にアメリカンオーク樽で熟成させていて、樽由来のバニラやスパイスのニュアンスが加わっているのが特徴よ。東急グループのソムリエたちが厳選した一樽を購入し、限定276本だけの特別な商品として仕上げられたの。

なるほど、アメリカンオーク樽での熟成はどんな効果があるんですか?
あと、限定276本ってかなり少ないですよね。どうしてそんなに限定したんでしょう?

アメリカンオークはフレンチオークに比べて樽香が強く、バニラやココナッツのような甘い香りがワインに加わるのが特徴よ。メルロの果実味とよく調和して、飲みやすくも深みのある味わいになるわね。
限定本数については、今回のプロジェクトが東急グループのソムリエたちの意見を反映した特別な選定品であることと、品質管理の面からも一樽分だけを使い切る形にしたからよ。希少性が高い分、消費者にとっても特別感があるわね。
ソムリエカンファレンスでの選定プロセスを振り返る

このワインの選定には約30名のソムリエが参加した2024年2月の「ソムリエカンファレンス」が大きな役割を果たしたの。多様な意見を集約し、最終的に6人の代表者が現地でテイスティングを行って決定したのよ。
こうした多角的な評価体制は、商品としての完成度を高めるうえで非常に効果的ね。涼くん、ソムリエが多数参加する選定会議ってどんなメリットがあると思う?

やっぱり、いろんな視点から評価できることが大きいと思います。味覚の好みは人それぞれですし、ソムリエそれぞれが異なる顧客層や利用シーンを想定して意見を出せるから、より多くの人に受け入れられるワインが選べるんですね。
それに、現地でのテイスティングは実際の環境や温度、香りの変化も感じられて、より正確な判断ができそうです。

そうなの。多様なソムリエの意見を反映することで、バランスの良いワイン選定が可能になるのよね。今回のように地域と企業が連携して商品開発を行う際には、こうしたプロセスが成功の鍵になるわ。
東急グループ4社の連携体制と販売戦略

東急グループは百貨店、スーパー、ホテルなど複数の業態を持っていますが、今回のワインはどのように販売されるんでしょうか?

今回の「信州 片丘メルロ 紫紺 2023」は、東急百貨店、ながの東急百貨店、東急ストア、東急ホテルズ&リゾーツの4社が連携して販売・提供するの。各社の異なる顧客層や利用シーンに対応できるように、販売チャネルを分散させているのが特徴ね。
例えば、百貨店ではギフト需要やワイン愛好家向けに、スーパーでは日常使いのワインとして、ホテルでは宿泊客への特別なサービスとして提供されるわ。こうした多角的な販売戦略は、商品を幅広い層に届けるうえで効果的よ。

なるほど、販売チャネルを分けることで、ワインの魅力を最大限に活かせるんですね。限定本数が少ないので、どのチャネルでも早めに売り切れそうですけど、購入できる場所が多いのはありがたいです。

そうね。販売開始は2025年6月からで、なくなり次第終了だから、気になる人は早めにチェックしたほうがいいわね。詳しくはHOTERES ONLINEの記事を参考にしてほしいわ。
「信州 片丘メルロ 紫紺 2023」の特徴と味わいのポイント

このワインの味わいについて、もう少し詳しく教えてください。メルロの特徴に加えて、どんな飲み方がおすすめですか?

メルロは一般的に柔らかくて丸みのあるタンニンが特徴で、果実味が豊か。今回の「信州 片丘メルロ 紫紺 2023」はアメリカンオーク樽熟成によるバニラやスパイスの香りが加わり、複雑さと深みが増しているわ。
飲み方としては、少し冷やし気味の16〜18度くらいで楽しむのがおすすめ。肉料理やチーズ、特に熟成タイプのものと相性が良いわね。涼くん、カクテル以外のワインの楽しみ方もぜひ知ってほしいわ。

はい、志乃さん。ワインは料理とのペアリングが大事だと聞きますが、具体的にどんな料理が合うか教えてもらえると嬉しいです。
あと、アメリカンオークとフレンチオークの違いももっと知りたいです。

メルロは比較的万能な品種だけど、特にローストビーフや鴨肉、マッシュルームを使った料理とよく合うわ。チーズならカマンベールやブリーなどのクリーミーなタイプが相性抜群ね。
オーク樽の違いについては、アメリカンオークはフレンチオークよりも香りが強く、バニラやココナッツのニュアンスが特徴。フレンチオークはより繊細でスパイシーな香りが出やすいわ。今回のワインはアメリカンオークの個性がしっかり感じられるから、味わいに力強さがあるのよ。
長野県塩尻市の「ドメーヌ コーセイ」ワイナリーについて

今回のワインを造った「ドメーヌ コーセイ」についても教えてください。どんなワイナリーなんでしょう?

ドメーヌ コーセイは長野県塩尻市にあるワイナリーで、地元の気候や土壌を活かした高品質なワイン造りに定評があるわ。塩尻市は標高が高く昼夜の寒暖差が大きいので、ブドウの糖度と酸味のバランスが良く、複雑な味わいのワインが生まれやすいの。
この地域は日本のワイン産地の中でも特に注目されていて、国内外のワイン愛好家から評価が高いのよ。今回の一樽はその中でも特に選りすぐりのものだったの。

そうなんですね。日本のワイン産地として長野はかなりポテンシャルが高いと聞いていましたが、ドメーヌ コーセイのようなワイナリーがあるのは心強いです。
これからもこうした地域のワイナリーが注目されるといいですね。

ええ、地域のワイナリーの活躍は日本のワイン文化の発展に欠かせないわ。今回のような企業との連携は、地元の魅力をさらに引き出すきっかけになるでしょう。
限定276本販売の意義と消費者へのメッセージ

限定276本という数量限定販売は、消費者にどんなメッセージを伝えているのでしょうか?

限定本数は希少性と特別感を演出する重要な要素よ。大量生産では味わえない、一樽一樽の個性を楽しんでほしいという想いが込められているの。
また、数量限定だからこそ、購入者はこのワインを手に入れた喜びや満足感をより強く感じられるわ。涼くん、限定品を扱う際に気をつけるべきポイントは何だと思う?

うーん、やっぱり情報の透明性と購入の公平性じゃないでしょうか。限定品は人気が集中しやすいので、どこで買えるか、いつ販売開始かを明確に伝えることが大事だと思います。
あと、品質のばらつきを防ぐための管理も重要ですよね。

その通り。今回のように東急グループが連携して販売することで、そうした課題にも対応しやすくなるわね。消費者にとっても安心して購入できる環境が整っているのは大きなメリットよ。
第2弾オリジナルワイン「信州たかやまワイナリー」との連携計画

ニュースでは第2弾のオリジナルワインが長野県高山村の「信州たかやまワイナリー」と連携して2025年秋に販売予定とありましたね。こちらについてはどういう展望がありますか?

第2弾も地域のワイナリーと連携して、東急グループの販路を活用しながら新たな魅力を発信する計画よ。信州たかやまワイナリーは高山村の自然環境を活かしたワイン造りをしていて、今回の片丘メルロとはまた違った個性が期待できるわ。
こうした継続的な連携は、地域ブランドの強化と消費者の選択肢拡大に寄与するから、今後も注目していきたいわね。

なるほど、東急グループが長野県内の複数のワイナリーと連携することで、地域全体のワイン文化が盛り上がりそうですね。これからも新しい商品が楽しみです。
北海道との新たな包括連携協定と今後の展望

さらに2025年5月には東急と北海道の包括連携協定も締結されて、今後は北海道産品の消費拡大にも取り組む計画があるの。北海道はワインだけでなく、ウイスキーやクラフトビールなど多様なお酒の産地としても注目されているわ。
涼くん、北海道のお酒産業についてはどう思う?

北海道は気候や自然環境が独特なので、個性的なお酒が多い印象です。ウイスキーの蒸留所も増えていて、クラフトビールも盛んですよね。こうした地域と企業の連携が進むと、さらに多様な商品が市場に出てきそうで楽しみです。
地域ごとの特色を活かしたお酒の発展は、消費者にとっても新鮮な体験になると思います。

そうね。地域連携は単なる販路拡大だけでなく、地域の文化やストーリーを伝える役割も担うから、お酒業界の未来にとって非常に重要なテーマよ。今回の東急グループの動きは、その先駆けとも言えるわね。
お酒業界における地域連携の重要性と未来予想図

今回の東急グループの取り組みを通じて、お酒業界における地域連携の重要性がよくわかりました。これからの業界はどう変わっていくと思いますか?

地域連携はこれからますます加速すると予想しているわ。地元の素材や技術を活かした商品開発が増え、消費者も産地の背景を重視する傾向が強まるからね。
また、企業が地域と協力して販路やマーケティングを強化することで、地方の小規模生産者も持続可能なビジネスモデルを築けるようになる。これが業界全体の活性化につながるのよ。

なるほど、地域の魅力を伝えることが商品の価値を高めるし、消費者もより豊かな体験ができるんですね。僕もSNSでこうした情報を発信して、もっと多くの人に知ってもらいたいです。

いい心がけね、涼くん。情報発信者としても、正確で深い知識を持つことが大切よ。今回のようなニュースをしっかり理解して伝えることで、読者にとって価値ある情報源になれるわ。
まとめ:東急グループの挑戦が示すお酒の新たな可能性

今回の東急グループと長野県の連携による「信州 片丘メルロ 紫紺 2023」の開発・販売は、地域資源を活かしたお酒づくりの新たな可能性を示しているわ。
地域のワイナリーと企業が協力し、多様な顧客層に向けた商品を提供することで、地域経済の活性化と消費者の満足度向上を両立しているのがポイントね。

志乃さん、今回のニュースを通じて、地域連携の重要性やワインの魅力をたくさん学べました。限定販売のワインは特別感があって、ぜひ味わってみたいです。
これからもこうした動きを追いかけて、みんなに伝えていきたいと思います。

ええ、涼くん。これからも新しい情報をキャッチして、正確に伝えていくことが大切よ。読者の皆さんにもぜひ、東急グループの取り組みや長野県産ワインの魅力を知ってもらいたいわ。



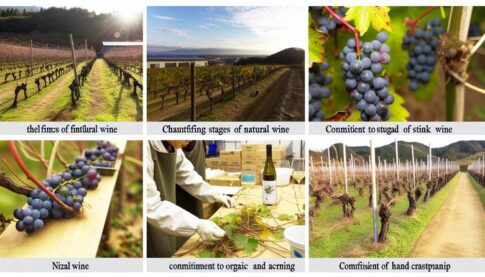







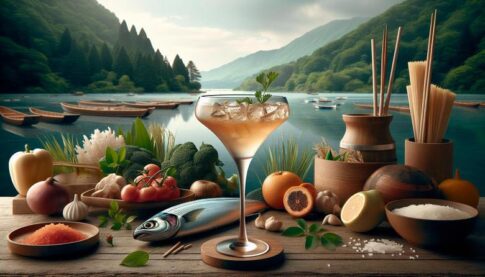









東急グループと長野県が2025年2月に締結した包括連携協定は、地域産品の販路拡大や消費促進を目的としたものよ。特に長野県産の農産物や工芸品、そして今回のようなワインなどの地元産品を東急グループの多様なチャネルで展開することが狙いね。
この協定により、長野県の魅力ある商品がより広く知られるようになるし、地域経済の活性化にもつながるわ。涼くん、こうした地域と企業の連携はお酒業界にとってどんな意味があると思う?