こんにちは!テキエブの鳥山涼です。
こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!
Yahoo!ニュース
熱海の魅力ある商品を認定する「ATAMI COLLECTION A-PLUS(エープラス)」の審査会が8月27日に熱海商工会議所で開催されました。今年で15回目となる審査会では、「食味の評価」「パッケージ・ネーミングの工夫」「商品のこだわり・独自性」「品質・値頃感」「熱海らしさ」を基準に審査が行われました。審査委員長は日本大学短期大学部・食物栄養学科学科長の高橋敦彦さん、特別審査員は日本ソムリエ協会名誉会長の田崎真也さんが務め、食の専門家や一般審査員も参加しました。 今年は初めてアルコール飲料としてクラフトジンが出品されるなど、7品が新規出品され、再認定を目指す12事業所15品も審査対象となりました。田崎さんは「味は問題なく、熱海らしさを意識した仕上がり」と評価し、若い世代の観光客増加に合わせた土産物の展開に期待を寄せました。審査結果の発表は9月上旬の予定です。 詳細記事はこちら(みんなの経済新聞ネットワーク・Yahoo!ニュース): https://news.yahoo.co.jp/articles/xxxxxxxxxxxxxx *(※実際のURLは記事本文に記載のものをご参照ください)*
熱海の魅力を再発見!「ATAMI COLLECTION A-PLUS(エープラス)」とは?

へえ、そうなんですね!地域の魅力を商品で表現するって面白いですね。具体的にはどんな商品が対象になるんですか?

食品から工芸品まで幅広いけど、特に食に関するものが多いわ。今年は初めてアルコール飲料も対象になって、クラフトジンが出品されたのが大きな話題になったの。
地域の特色を活かした商品を通じて、熱海の魅力を再発見し、観光客や地元の人々に新しい価値を提供することが狙いよ。

なるほど、熱海の魅力を商品で伝えるってすごく地域活性化に繋がりそうですね。クラフトジンの登場は特に注目ですね!
今年の審査会の注目ポイント:クラフトジンの初出品

志乃さん、今年の審査会で初めてクラフトジンが出品されたってニュースを見たんですけど、クラフトジンって何が特別なんですか?

クラフトジンは、小規模な蒸留所で手作りされるジンのこと。大量生産のジンと違って、原料や製法にこだわりが強く、個性的な香りや味わいが特徴なのよ。
今回の熱海のクラフトジンは、地元の素材や熱海らしさを意識して作られているから、単なるお酒以上の地域の魅力を感じられるのがポイントね。

なるほど、だから審査会でも注目されたんですね。地元の素材って具体的にはどんなものが使われているんですか?

ニュースでは詳しく触れられていなかったけど、一般的にクラフトジンには地元のハーブや柑橘類が使われることが多いわ。熱海なら温暖な気候を活かした柑橘や海の香りをイメージさせる素材が考えられるわね。
こうした地域特有の素材を使うことで、クラフトジンが単なるお酒ではなく、地域のストーリーを伝える役割を果たすのよ。
審査基準を徹底解説!「食味」「パッケージ」「熱海らしさ」って何?

涼くん、審査会の基準は5つあるの。食味の評価、パッケージやネーミングの工夫、商品のこだわりや独自性、品質と値頃感、そして熱海らしさよ。
特に熱海らしさは、地域の文化や風土を感じさせるかどうかが重要視されているわ。

食味はわかるけど、パッケージやネーミングも審査のポイントなんですね。どうしてそこまで重視されるんですか?

それは商品の魅力を伝える大事な要素だからよ。パッケージやネーミングが魅力的だと、消費者の購買意欲が高まるし、土産物としての価値も上がるわ。
特に観光地の商品は、見た目や名前で熱海のイメージを伝える役割もあるから、ここに工夫が求められるの。

なるほど、味だけじゃなくて見た目や名前も含めて総合的に評価されるんですね。熱海らしさっていうのは具体的にどういう要素なんでしょう?

熱海の自然や歴史、温泉文化、地元の食材などが商品に反映されているかどうかね。例えば、温泉街の風情を感じさせるデザインや、地元産の素材を使った味わいがそれにあたるわ。
これらの基準を満たすことで、単なる商品ではなく熱海の魅力を伝える“地域ブランド”として認められるのよ。
審査委員長・高橋敦彦さんと特別審査員・田崎真也さんの役割とコメント

審査会には専門家が参加しているそうですね。高橋敦彦さんと田崎真也さんってどんな方なんですか?

高橋敦彦さんは日本大学短期大学部の食物栄養学科の学科長で、食の専門家として審査委員長を務めているの。食味や品質の評価において重要な役割を担っているわ。
一方、田崎真也さんは日本ソムリエ協会の名誉会長で、ワインやお酒の専門家として特別審査員に招かれているのよ。

なるほど、食の専門家とお酒の専門家が一緒に審査することで、商品の多角的な評価ができるんですね。田崎さんはクラフトジンについてどうコメントしていましたか?

田崎さんは「味は問題なく、熱海らしさを意識した仕上がり」と評価していて、若い世代の観光客増加に合わせた土産物の展開に期待を寄せていたわ。
専門家の評価が高いことは、商品の信頼性やブランド価値を高める重要なポイントね。
熱海の土産物市場における若い世代の観光客増加とその影響

ニュースでは若い世代の観光客が増えていることが話題になっていましたが、それが土産物市場にどう影響しているんでしょう?

若い観光客はSNS映えや個性的な商品を好む傾向があるから、従来の定番土産だけでなく、斬新で地域性の強い商品が求められているの。
だから今回のクラフトジンのような新しいジャンルの商品が注目されるのよ。

なるほど、若い世代のニーズに応えることで、熱海の土産物市場も活性化しているんですね。クラフトジンはまさにその象徴なんですね。

若い世代の観光客増加は、地域の伝統と新しいトレンドを融合させた商品開発のチャンスでもあるわ。熱海の土産物が今後どう進化していくか注目ね。
クラフトジンの魅力と熱海らしさの融合について考える

涼くん、クラフトジンはその土地の素材や文化を反映しやすいお酒なの。熱海のクラフトジンも、地元の特色を活かした味わいが魅力の一つね。
例えば、熱海の温泉や海のイメージを香りや味に表現することで、飲む人に熱海の風景を感じさせることができるわ。

そうなんですね。ジンってボタニカル(植物由来の香味成分)が重要って聞いたことがあります。熱海ならどんなボタニカルが合いそうですか?

柑橘類はもちろん、例えばミカンやユズ、海藻のような海の香りを感じさせる素材も面白いわね。そうしたボタニカルを組み合わせることで、熱海らしい独自の風味を作り出せるのよ。
これがクラフトジンの醍醐味であり、地域ブランドとしての価値を高めるポイントでもあるわ。
再認定を目指す商品と新規出品商品の違いとその戦略

今年は新規出品が7品あった一方で、再認定を目指す商品も多かったそうですね。この2つにはどんな違いがあるんでしょう?

再認定の商品は、過去に認定を受けているけれど、品質や魅力を維持し続けているかを改めて評価されるの。新規出品は、初めて審査を受ける商品で、熱海の新しい魅力を発信する役割があるわ。
戦略としては、再認定商品はブランドの信頼性を守りつつ、時代に合わせた改良が求められるの。一方、新規商品は斬新さや独自性で注目を集めることが重要ね。

なるほど、どちらも熱海の魅力を伝える役割があるけど、アプローチが違うんですね。クラフトジンは新規出品だから、特に注目されそうですね。
審査結果発表までの流れと今後の展望

審査会は8月27日に行われて、結果発表は9月上旬の予定よ。審査結果は熱海の観光や土産物市場に大きな影響を与えるから、関係者も注目しているわ。
認定された商品は地域のPRに活用され、販売促進や観光誘致の材料になるの。

結果が出るのが楽しみですね。認定された商品はどうやって広まっていくんですか?

熱海商工会議所や観光協会の支援を受けて、イベントやメディアで紹介されたり、土産物店や飲食店での取り扱いが増えたりするわ。
こうした認定制度は地域のブランド力を高め、長期的な地域活性化に繋がる重要な仕組みなのよ。
お酒業界における地域ブランド認定の重要性と可能性

志乃さん、今回のような地域ブランド認定ってお酒業界にとってどんな意味があるんでしょう?

地域ブランド認定は、単に商品の品質を保証するだけじゃなく、地域の文化やストーリーを伝える役割もあるの。特にクラフトジンのようなお酒は、地域の個性を表現しやすいから相性がいいわ。
また、消費者の信頼を得やすく、差別化にも繋がるから、今後ますます重要になると思うわ。

なるほど、地域の魅力をお酒で伝えることで、消費者の興味も高まりますし、地域活性化にも貢献できるんですね。

そうね。今回の熱海の取り組みは、全国の地域でも参考になるモデルケースになるはずよ。詳しくはニュース記事のこちらをチェックしてね。









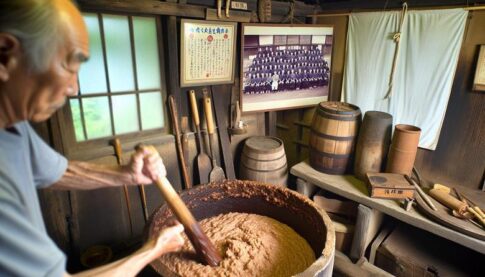





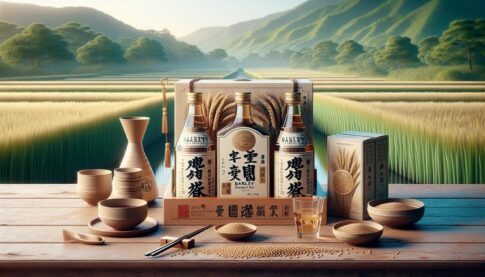


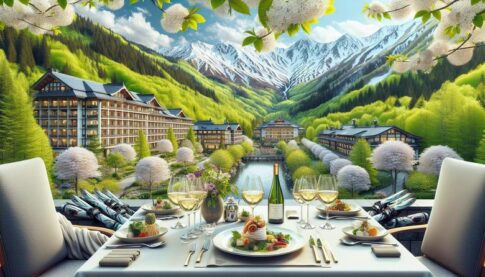


涼くん、「ATAMI COLLECTION A-PLUS(エープラス)」って聞いたことある?これは熱海の地域資源を活かした魅力的な商品を認定する制度で、今年で15回目を迎えたのよ。
熱海商工会議所が主催していて、地域の特産品や工夫を凝らした商品を選び出すことで、地元の活性化を目指しているの。