こんにちは!テキエブの鳥山涼です。
こちらのニュースについて、志乃さんと話しました!
【日本ワインを知る・味わう】日本固有品種「山幸」と「龍眼」をテーマに、研究者・生産者が語るイベントを開催
一般社団法人OIV登録品種協議会は、2025年12月6日(土)に東京都の全国町村会館で「第7回OIV登録品種サミット」を開催します。本イベントでは、日本固有のブドウ品種「山幸」(北海道中心)と「龍眼」(長野県中心)に焦点を当て、研究者や生産者、流通関係者、ワイン愛好家が一堂に会し、それぞれの品種の歴史や特徴、OIV(国際ブドウ・ワイン機構)登録の意義、今後の展望について議論します。 プログラムは、長野県の「龍眼」に関わる専門家や生産者による講演、北海道十勝地方の「山幸」生産者を交えたパネルディスカッション、そして2027年に誕生100年を迎える「マスカット・ベーリーA」についての次回予告で構成されます。後半のテイスティングセッションでは、「山幸」と「龍眼」を中心に日本固有品種から造られた約15種のワインを、チーズやPasco社の冷凍パン「L’Oven」とともに自由に試飲できます。 OIV登録は、国際的な認知度向上やEUへの輸出時の品種表示が可能になるなど、日本ワインの品質向上に寄与しています。主催は一般社団法人OIV登録品種協議会で、協力団体にはNPO法人チーズプロフェッショナル協会、敷島製パン株式会社、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所、岩の原葡萄園、ワインアンドワインカルチャー株式会社が名を連ねています。 参加費は8,000円、定員80名で途中入退場自由。テイスティンググラス付きです。詳細およびチケット購入は以下のURLから可能です。 https://peatix.com/event/4611653/view イベント会場のアクセス情報はこちら: https://www.zck.or.jp/kaikan/access/ 一般社団法人OIV登録品種協議会公式サイト:
一般社団法人OIV登録品種協議会登壇者には、マンズワイン常任顧問の松本信彦氏、長野県地酒・食品振興課の高橋祐樹氏、長野県ワイン協会理事長の武田晃氏、めむろワイナリー代表の尾藤光一氏、相澤ワイナリー代表の相澤一郎氏、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所所長の南邦治氏、ワインアンドワインカルチャー代表の田辺由美氏、岩の原葡萄園社長の高岡成介氏らが名を連ね、日本ワインの未来を多角的に語ります。
「第7回OIV登録品種サミット」開催の概要と注目ポイント

なるほど、志乃さん。日本のワイン品種に特化したイベントって珍しいですよね。参加者はどんな人たちが集まるんですか?
あと、イベントの内容や参加方法についても教えてください。

参加者は専門家だけでなく、ワイン愛好家や流通関係者も含まれているわ。講演やパネルディスカッション、そしてテイスティングセッションもあるから、知識を深めるだけでなく実際に味わいながら学べるのが魅力ね。
参加費は8,000円で定員は80名。途中入退場も自由で、テイスティンググラスも付いてくるわ。詳しくはこちらの公式ページで確認できるから、興味があれば早めにチェックしてみて。
日本固有品種「山幸」と「龍眼」の特徴と歴史を語る

志乃さん、「山幸」と「龍眼」ってどんな品種なんですか?名前は聞いたことありますけど、詳しくは知らなくて。
それぞれの特徴や歴史について教えてもらえますか?

いい質問ね。まず「山幸」は北海道の十勝地方を中心に栽培されている日本固有のブドウ品種で、冷涼な気候に適応しているのが特徴よ。酸味がしっかりしていて、繊細な香りが楽しめるワインになるわ。
一方、「龍眼」は長野県を中心に栽培されている品種で、やや甘みがありつつもバランスの良い味わいが特徴。歴史的には長野の地酒文化と深く結びついていて、地域のワイン造りに欠かせない存在になっているの。

なるほど、地域の気候や文化に根ざした品種なんですね。そういう背景を知ると、ワインを飲む時の楽しみ方も変わりそうです。
それに、こうした品種が国際的に認められることってすごく大事なんですね。
OIV登録の意義と日本ワインの国際的評価向上について

そう、OIV(国際ブドウ・ワイン機構)への登録は国際的な認知度を高める重要なステップなの。これにより、EUをはじめとした海外市場で品種名を表示できるようになり、日本ワインのブランド価値向上に繋がるわ。
また、品質の証明としても機能するから、消費者の信頼を得やすくなるのよ。

なるほど、単に名前が登録されるだけじゃなくて、輸出や品質保証にも影響があるんですね。
日本ワインの世界進出にとっては欠かせないプロセスなんだとわかりました。

その通り。日本のワイン産業全体の底上げにもつながるから、今回のサミットでの議論は業界にとっても大きな意味を持つわね。
登壇者紹介:研究者・生産者が語る日本ワインの未来

今回のサミットにはどんな方々が登壇されるんですか?名前を聞くだけでもすごそうですね。
どんな話が聞けるのか楽しみです。

登壇者には、マンズワイン常任顧問の松本信彦氏や長野県ワイン協会理事長の武田晃氏、めむろワイナリー代表の尾藤光一氏など、業界の第一線で活躍する方々が揃っているわ。
彼らはそれぞれの専門分野から日本ワインの現状や課題、未来の展望について多角的に語る予定。生産者のリアルな声や研究者の最新知見が聞ける貴重な機会よ。

それは貴重ですね。実際にワインを造っている方や研究者の話を聞くことで、より深く日本ワインの魅力を理解できそうです。
志乃さんは特に注目している登壇者はいますか?

そうね、特に池田町ブドウ・ブドウ酒研究所の南邦治所長は、北海道の「山幸」についての研究をリードしているから注目しているわ。地域の特性を活かしたワイン造りの話はとても興味深いはずよ。
テイスティングセッションの魅力とおすすめペアリング紹介

サミットの後半にはテイスティングセッションもあるそうですね。どんなワインが試飲できるんですか?
また、ペアリングのおすすめもあれば教えてください。

テイスティングでは「山幸」と「龍眼」を中心に、日本固有品種から造られた約15種類のワインが楽しめるわ。これに合わせて、NPO法人チーズプロフェッショナル協会監修のチーズや、Pasco社の冷凍パン「L’Oven」も提供されるの。
ワインとチーズ、パンの組み合わせは味わいの相乗効果を生み出すから、ぜひじっくり味わってほしいわね。

チーズとパンとワインの組み合わせは最高ですね!特に日本固有品種のワインと合わせると、どんな味わいになるのか想像が膨らみます。
初心者でも楽しめるペアリングのコツとかありますか?

初心者なら、酸味がしっかりした「山幸」にはクリーミーなチーズを合わせるとバランスが良いわ。甘みのある「龍眼」には少し塩気のあるパンやチーズが相性抜群よ。
テイスティングは自由に試せるから、自分の好みを探しながら楽しむのが一番ね。
「マスカット・ベーリーA」100周年に向けた展望と次回予告

今回のサミットでは、2027年に誕生100年を迎える「マスカット・ベーリーA」についても触れられるそうですね。
この品種の歴史や今後の展望について教えてください。

「マスカット・ベーリーA」は日本を代表する赤ワイン用ブドウ品種で、1927年に誕生して以来、日本のワイン文化を支えてきた重要な存在よ。
100周年を迎えるにあたり、次回のサミットではその歴史や進化、そして未来への期待が語られる予定。日本ワインの伝統と革新を象徴する品種として注目されているわ。

なるほど、歴史ある品種の節目の年に向けて、今から盛り上がっているんですね。次回のサミットも楽しみです。
日本ワインの多様性と可能性を感じます。
参加方法・会場アクセスとイベントの楽しみ方ガイド

参加方法は簡単よ。公式のチケット販売サイトPeatixページから申し込めるわ。定員80名だから、興味があるなら早めの予約がおすすめね。
会場は全国町村会館で、アクセス情報はこちらで確認できるわ。

途中入退場自由というのも嬉しいポイントですね。仕事帰りや予定の合間にも参加しやすそうです。
志乃さん、イベントを最大限楽しむコツはありますか?

まずは講演やパネルディスカッションで知識を深めて、その後のテイスティングで実際に味わいながら理解を深めることね。
また、参加者同士の交流も貴重な情報交換の場になるから、積極的に話しかけてみるといいわ。
補足解説:日本ワインの基礎知識と品種の多様性について

志乃さん、日本ワインって品種が多いんですか?外国のワインと比べてどう違うんでしょう?
基礎的なことも教えてもらえると助かります。

日本ワインは気候や土壌の多様性から、多くの品種が栽培されているのが特徴よ。特に固有品種は日本の風土に適応していて、独特の味わいを持っているわ。
例えば「山幸」や「龍眼」のように地域に根ざした品種が増えてきているのは、日本ワインの個性を強める動きと言えるわね。
こうした多様性が日本ワインの魅力であり、世界に誇れるポイントなの。

なるほど、品種の多様性が味わいの幅を広げているんですね。これから日本ワインをもっと知っていきたいと思いました。
志乃さん、今日はありがとうございました!

こちらこそ、涼くん。これからも一緒に日本のお酒文化を深めていきましょうね。





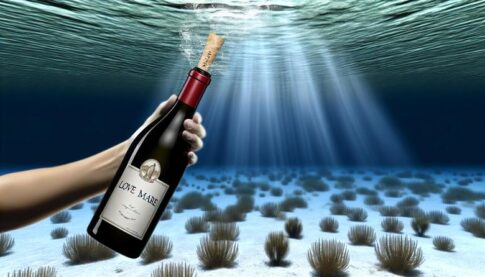
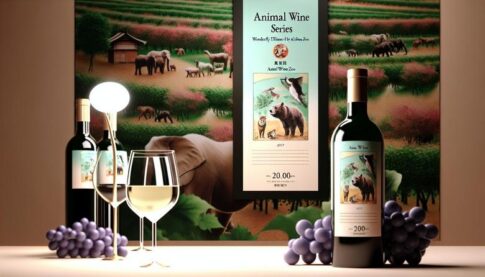








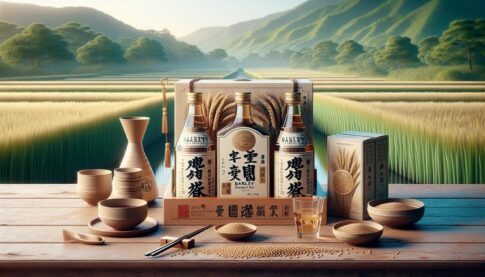


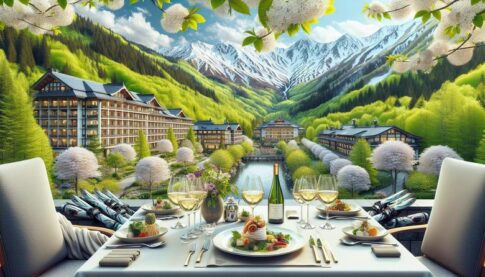


2025年12月6日に東京都の全国町村会館で「第7回OIV登録品種サミット」が開催されるのをご存知?このイベントは、日本固有のブドウ品種に焦点を当てて、研究者や生産者、流通関係者、そしてワイン愛好家が一堂に会する貴重な機会よ。
特に今回は北海道中心の「山幸」と長野県中心の「龍眼」という2つの品種にスポットを当てているのが特徴ね。日本ワインの未来を語る上で非常に重要なイベントと言えるわ。